放置すると治りにくくなることも。お尻の悩み「痔」は、専門医に相談して漢方併用で症状改善を
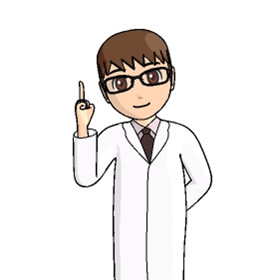
青松記念病院 副院長 青松 直撥 先生
悩みは深刻なお尻のトラブル「痔」、その3タイプ
新型コロナウイルス感染症の流行期間中、排便後の出血などの気になるお尻の症状があっても、受診を控えていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。2023年5月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが2類感染症から5類感染症に移行して以降、悪化したお尻の症状に困って当院を受診される患者さんが増えています。
今回は、お腹の不調のなかでもなかなか相談しづらく、ついがまんしがちなお尻のトラブルについて解説します。代表的なお尻のトラブルに「痔」があります。排便後に出血があったり、いぼが出てしまい指で戻さなければいけない、自転車に乗っているとはみ出たいぼがお尻とサドルの間に挟まっている感じがしたりするなど、痔の悩みは深刻です。
痔には、いぼ痔や切れ痔、あな痔の3つのタイプがあります。医学的にはそれぞれ、痔核(じかく)、裂肛(れっこう)、痔ろうといいます。生活習慣の乱れや運動不足から便秘がちになると、コロコロの便が出るようになり、排便時のいきみが自然と多く、強くなります。過剰ないきみが繰り返されると、肛門クッションと呼ばれる痔核組織の腫れや脱出、傷ついた粘膜からの出血につながり、痔核や裂肛の原因になるのです。お尻のトラブルに気づいたら、早めに肛門専門医を受診しましょう。
よくあるお尻の悩み
- いぼ痔(内痔核)
- 切れ痔(裂肛)
- あな痔(痔ろう)
肛門の仕組み
肛門(肛門管)は、胃や腸から続く消化管の出口にあたる長さ約3cmほどの器官で、直腸からつながっています。直腸では痛みを感じませんが、肛門は皮膚と同じく痛みを感じる神経が通っています。痔のできる場所によって、痛みなどの自覚症状が異なります。
肛門は括約筋(かつやくきん)の働きによって排便時以外は締められていますが、筋肉と粘膜だけでピタリを閉じることができず、隙間ができてしまいます。この隙間をふさいでいるのが「肛門クッション」です。肛門クッションは、肛門の粘膜下の血管や筋線維が結合してできています。肛門クッションは加齢に伴い老化し、排便時の圧力で血管が腫れあがるようになります。これが痔核の原因です。
いぼ痔(内痔核)
なかでも悩んでいる方が多いのは、いぼ痔と呼ばれる内痔核です。内痔核は、肛門クッションの血管が切れて出血したりうっ血していぼのように出てきた「痔核」のなかでも、直腸側にできたものです。直腸の粘膜にできているので、通常は痛みを感じません。出血や、痔核が肛門から出てしまう脱肛(だっこう)があって気づくことがほとんどです。
命に関わるような病気ではないため、気になる症状があっても長年放置されている方もいらっしゃいます。しかし、次第に便が出にくくなったり、排便のたびに便器が真っ赤になるほどの出血があるという方もいて、放置すればするほど痔の症状は進行してしまいますから、がまんを続けないようにしていただきたいものです。
いぼ痔の治療では、症状が軽い場合には塗り薬や漢方による治療で良くなることもあります。進行すると、ジオン硬化療法(痔核硬化療法)という、内痔核に薬剤を注入して硬くして粘膜に癒着・固定させる治療や、根治手術が必要となります。
切れ痔(裂肛)
切れ痔と呼ばれる裂肛は、便秘気味の女性に多いお悩みです。排便をがまんしたり、便秘がちで硬い便が出た際に、お尻が切れて起こります。出血は紙につく程度ですが、強い痛みを伴います。そのため、排便をがまんしてしまって便秘になり、症状を悪化させることもあります。
お尻の切れた部分が治る過程でお尻が痛くなったり、硬い便が出てお尻が切れるのを繰り返しているうちに肛門が狭くなってしまい、余計に排便しにくくなる場合もあります。肛門が狭くなると手術が必要になる場合もあります。
あな痔(痔ろう)
あな痔と呼ばれる痔ろうは、何度も切れ痔を繰り返しているうちに肛門周囲が細菌に感染して炎症を起こし、穴ができてそこから膿(うみ)が出ている状態です。若年~中年男性からの相談が多い印象があります。熱が出たり、肛門周囲の痛みを伴います。
治療によって一時的によくなる方もいらっしゃいますが、再発しやすく、穴が増えて痔ろうが複雑化していくと、手術も難しくなりますし、重症の場合は人工肛門が必要なることもあります。早期に、そして症状が軽いうちに治療をすることが大切です。早めに治療を開始すれば、抗生剤や生活習慣の改善などで症状を改善できます。
基本的な西洋医学の治療に漢方を追加し、相乗効果を期待
痔でお悩みの患者さんに漢方による治療を提案する場合、切れ痔(裂肛)やいぼ痔(内痔核)の患者さんには 乙字湯(おつじとう)をよく使います。乙字湯には生薬の大黄が含まれていますので、特に便秘がちで肛門にうっ血があるような患者さんには、便を柔らかくして肛門のうっ血を和らげ、排便をスムーズにする効果や、痔そのものの縮小効果を期待して処方します。乙字湯を使う場合は、強力ポステリザン軟膏も併用しています。痔核硬化療法や手術を行った場合でも、患者さんから服薬中止の申し出があるまでは、術後も強力ポステリザン軟膏と乙字湯を継続しています。ただし、腹痛や下痢がでる場合がありますので、処方の際には患者さんに注意を促しています。
あな痔(痔ろう)は感染性の疾患ですので、消炎剤や抗生剤による治療が基本です。当院ではこれに、十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)を併用することが多くあります。十味敗毒湯は、膿が出るような皮膚症状を改善するためによく用いられる漢方ですから、穴痔から出る膿の改善を期待して処方します。
お尻の不調に処方する漢方薬の例
漢方薬は食前や食間に服用するようにとよく言われています。そのため飲み忘れを気にされる患者さんもいらっしゃいますが、服用のタイミングにそれほど厳格にならなくても大丈夫です。1日2回の製剤であれば、朝は起きた時に飲み、夕食前に飲み忘れてしまったら、寝る前に飲んでくださいとお伝えしています。飲み忘れないように服薬を継続することが、症状改善につながります。
また、痔の再発を予防するには、毎日の生活習慣を見直すことも必要です。便意をもよおしたらがまんせず、トイレに行きましょう。トイレではいきみ過ぎないように注意し、なるべく短時間で済ませるようにしてください。食生活では便秘や下痢にならないように、毎日の食事で食物繊維を意識的に摂りましょう。お酒や唐辛子などの香辛料は肛門を刺激して炎症の原因になります。アルコールや刺激物は控えめを心掛けるとよいでしょう。肛門が不潔だと細菌が繁殖するため、温水洗浄式便座の使用やシャワーで軽く洗い流すなどして、お尻を清潔に保つよう心掛けてください。肛門部分の血行が悪化すると痔になりやすくなりますから、腰回りを冷やさないように注意しましょう。お風呂に入って血行をよくすることも、痔の予防につながります。座りっぱなしや立ちっぱなしも、肛門をうっ血させるため痔の原因になります。長時間同じ姿勢をとらないようにしてください。運動不足は便秘につながりますから、適度な運動を心掛けることも大切です。
気になる症状があるなら、専門医のいる医療機関で相談を
お尻の悩みを抱えていらっしゃる方は多いと思います。女性の場合は出産を機に痔が悪化する方もいらっしゃいます。ところが、お尻の悩みだけに、なかなか病院に行けなかったり相談できなかったりしている方が大勢いるのが現実です。当院を受診される患者さんの中にも、悩みに悩んで症状が悪化してから初めて受診される方もいます。
お尻からの出血は、痔が原因とは限りません。大腸がんや大腸ポリープ、クローン病などほかの病気が隠れていることもあります。まずは、気になる症状があれば早めに医療機関を受診してほしいですね。早めに受診し、早めに治療を開始できれば、症状もよくなりやすいものです。日本臨床肛門病学会では、痔の治療を専門的に行っている施設を認定し、一般の方に広く紹介(※)しています。当院も認定施設の一つです。一人で悩まず、日本臨床肛門学会認定施設のような専門医のいる医療機関に相談し、適切な治療を受けることをお勧めします。
※ 日本臨床肛門病学会 痔を専門とする病院を探そう をぜひご覧ください。
青松記念病院
副院長 青松 直撥 先生
お腹の不調 関連するその他の情報
-
漢方Q&A
-
漢方Q&A
-
暮らしの不調
-
暮らしの不調
お腹の不調 関連する代表的な漢方薬
